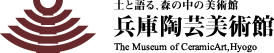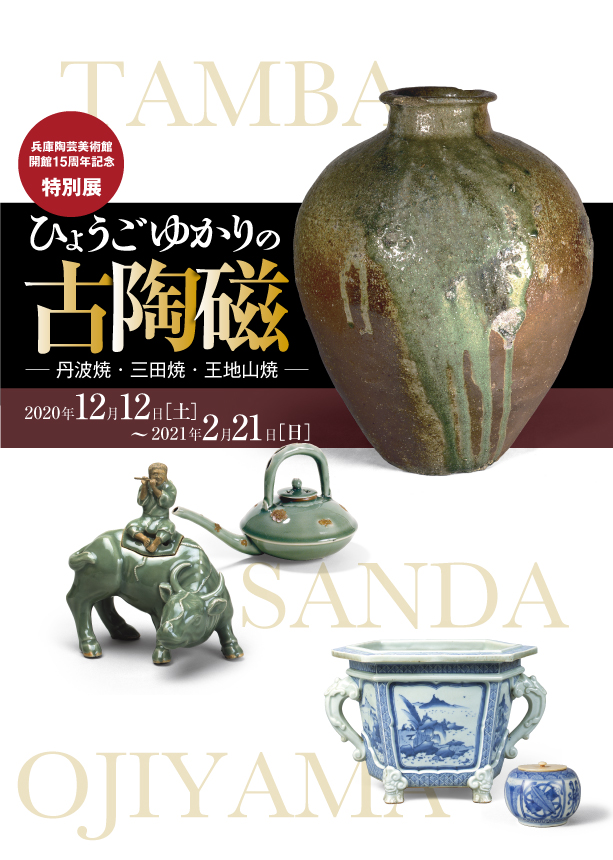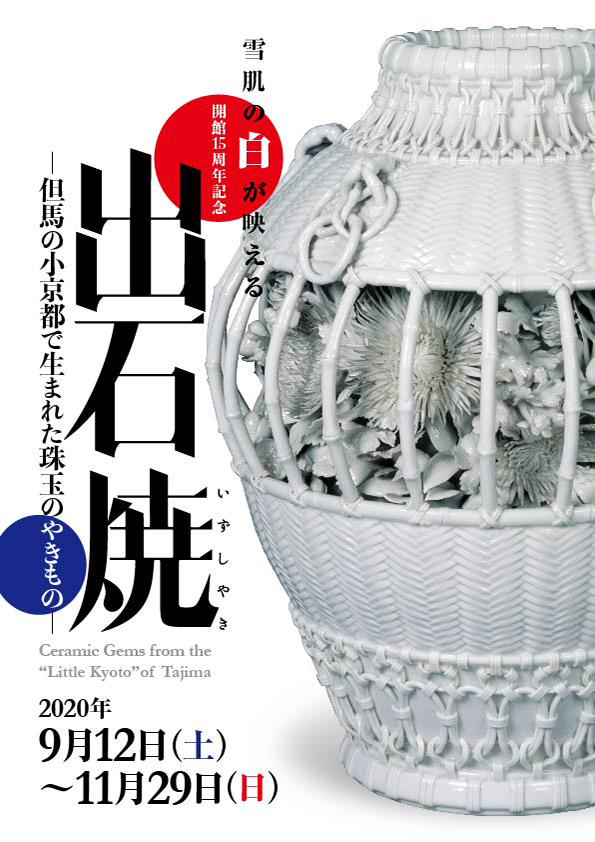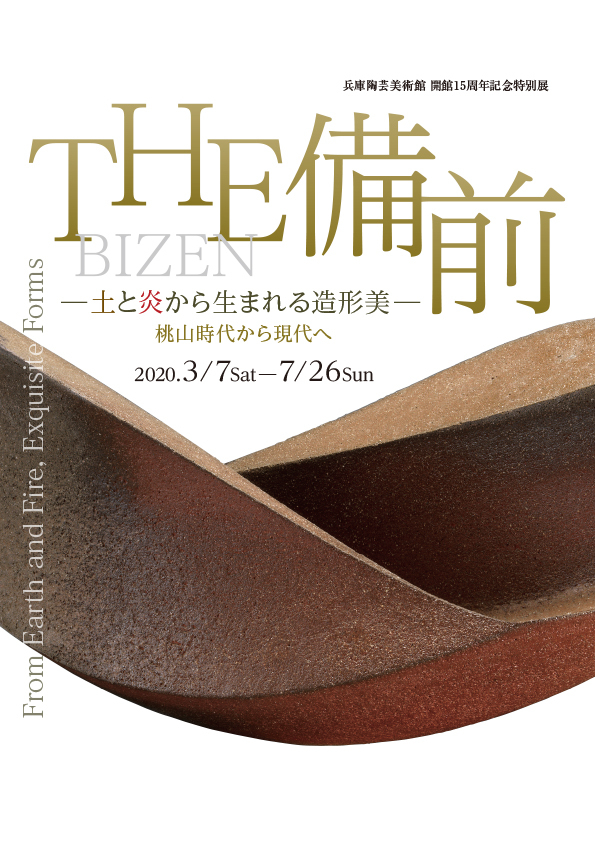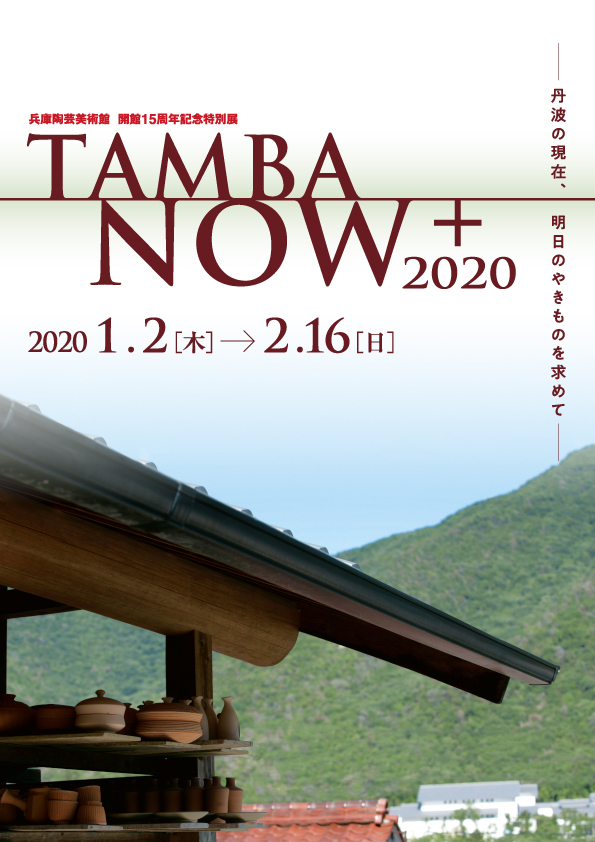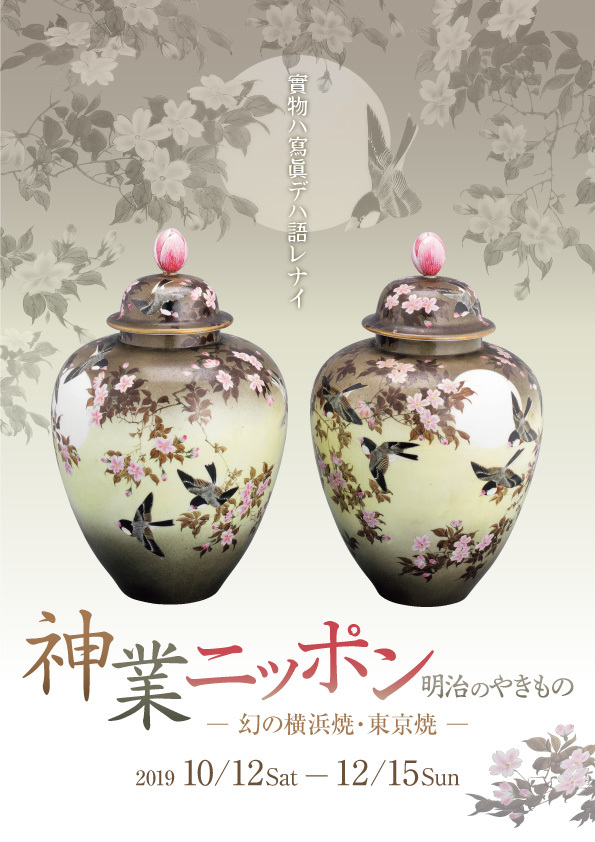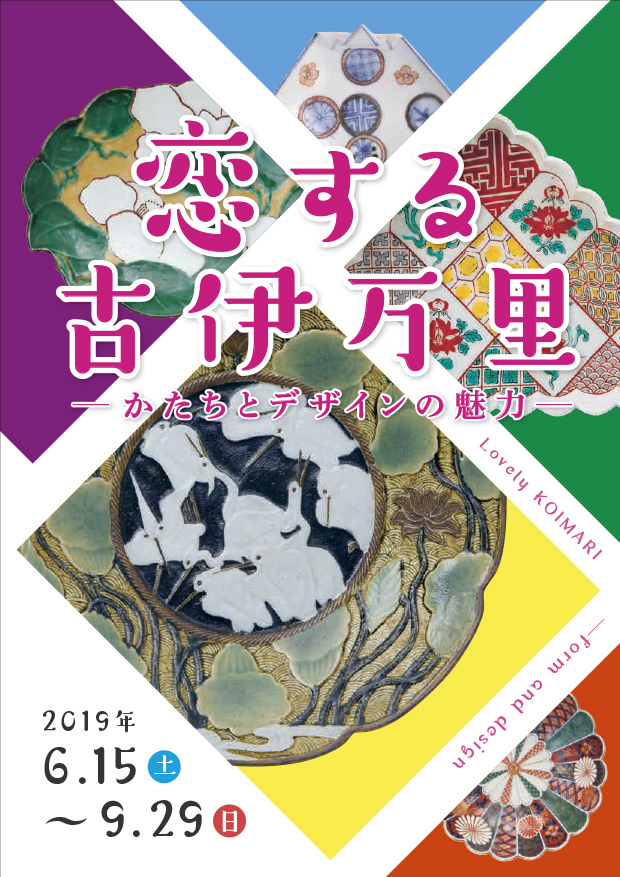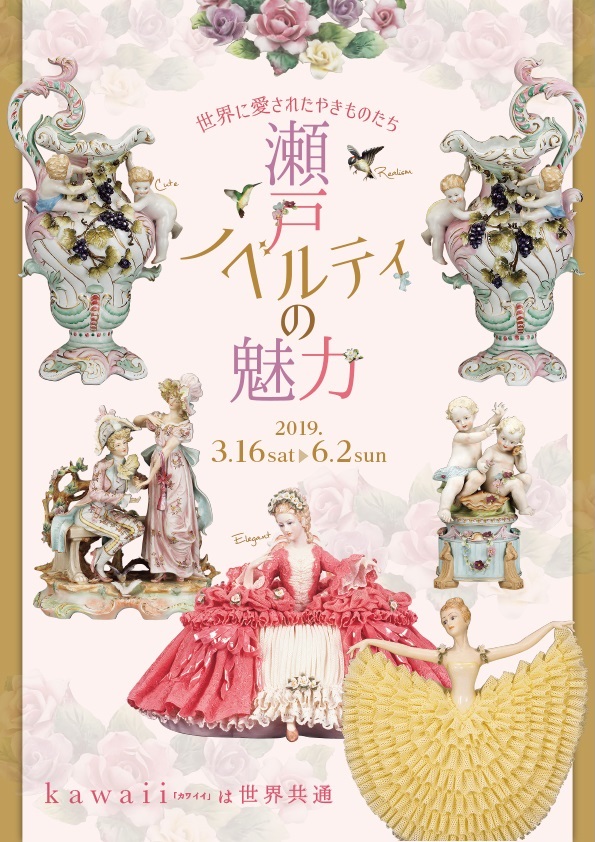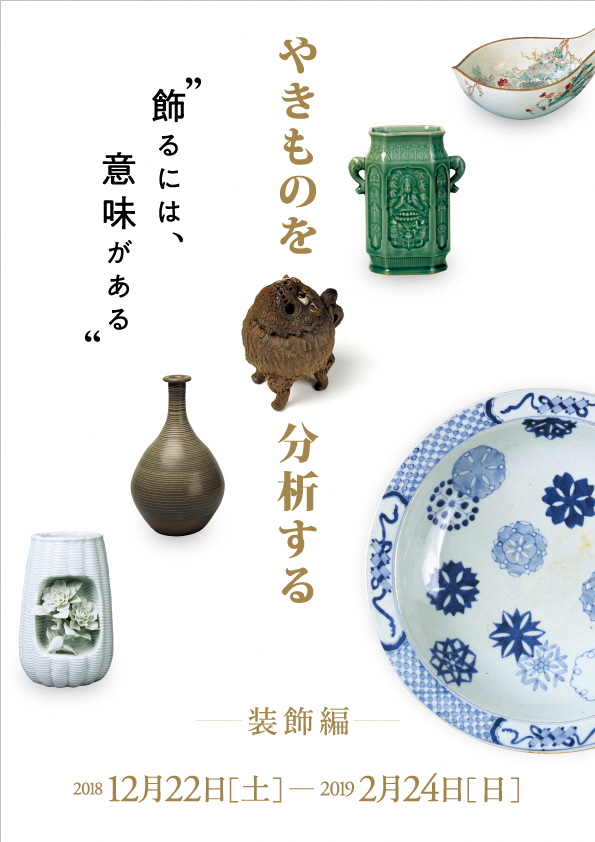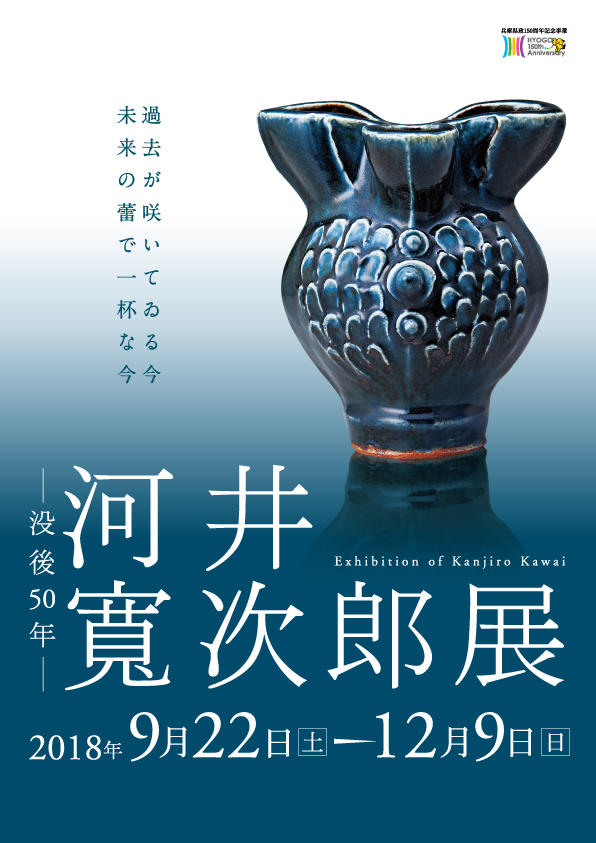- バリアフリー情報
- プレスリリース
- ムーミンの食卓とコンヴィヴィアル展 ―食べること、共に生きること―
- レストラン
- 丹波焼の里情報
- 丹波焼の里 ミュゼレター
- 最古の登窯復興
- 最古の登窯レポート
- 窯元路地歩き
- 美術館周辺のご案内
- 美術館について
- コレクション
- お問い合わせ
- リンク
- プライバシーポリシー
- English
- Exhibitions
- お知らせ
- これまでの展覧会情報
- ご利用案内・アクセス
- ご利用案内
- 観覧料
- 当館へのアクセス
- よくあるお問い合わせ
- 団体受付
- 団体受付用フォーム
- セミナー室・談話室利用料金
- コミュニティギャラリー
- ワンコインコンサート《現在演奏者の受付は停止中です》
- イベント
- イベント情報の一覧
- これまでのイベント情報
- コミュニティギャラリー
- 講座・学校プログラム
- 著名作家招聘事業
- 講座・ワークショップ
- これまでの講座・ワークショップ
- 学社連携プログラム
- 博物館実習
土と語る、森の中の美術館 兵庫陶芸美術館 The Museum of Ceramic Art, Hyogo